金融機関が住宅ローンの融資金額を決定する際には、返済負担率(その人の税込年収に対する住宅ローンの年間返済額の割合)を一つの判断基準としています。
たとえば、年収500万円の人の年間返済額が125万円の場合、返済負担率は、
125万円 ÷ 500万円 = 0.25
となり、返済負担率は25%という計算になります。
各金融機関でこの基準は異なりますが、最大で年収負担を30〜35%を融資の上限としているところが多く、一般的に返済負担率は20〜25%以内に収めるのが望ましいとされています。
年収が低く、適正な返済負担率に満たない場合には希望している金額が借りられない場合があります。
その際にいくつの選択肢がありますのでご紹介します。
収入合算制度を利用する

まず、利用を検討してみたいのが、夫だけではなく妻の収入も考える『収入合算制度』です。
配偶者や、親・子などの一定の条件を満たした、近親者の収入を合算して算定できる制度です。
対象は以下の通りです。
- 申込本人の配偶者、父母、子供などの直系親族、婚約者、内縁関係
- 収入を証明する公的証明書を提出できる
- ローンの連帯責務者、または連帯保証人になれる年齢は70歳未満
『収入合算制度』を利用する場合、大きく『連帯責務』と『連帯保証』の2通りのパターンがあります。
連帯責務
夫婦で借りる場合、ローン契約者は夫と妻の両者になります。
夫婦の収入を合算して借り入れ、妻は連帯債務者となりますが、返済は夫がまとめて行います。
妻は返済義務を負う事になりますが、毎月返済をする必要はありません。
住宅ローン審査は夫の収入と妻の収入の合計額を審査し融資可能額が決定します。
連帯債務は、基本的に年収の高い方の契約者をメインの債務者とし、年収の少ない方の契約者は年収の半分程度を融資対象にするといったパターンが多いです。
連帯債務を認めているのは、原則フラット35だけですが、連帯債務者は住宅ローン減税を受けられます。
連帯保証
夫婦で借りる場合、契約者は夫で、夫の収入と妻の収入の合計で融資を受けますが、返済するのは夫のみです。
妻は夫が返済できなくなった時だけ返済の義務を負います。
つまり連帯保証人になる形で契約を行いますので、妻は住宅ローン減税を受けられません。
連帯保証は、実際にローンを組むのは、夫(あるいは妻)だけで、もう一方の人はローンの返済が滞った時だけ返済義務を負うという物です。
子供が生まれたり等で将来仕事を辞める可能性がある場合には連帯債務より、こちらの選択が良いです。
ペアローン
夫婦共働きであれば、夫婦それぞれの名義でローンを借り、それぞれが返済をする『ペアローン』という選択肢もあります。
住宅ローンの契約は夫と妻、各1本、合計2契約になります。
ペアローンは夫婦それぞれで借り入れをし、返済も別々にする方法なので、夫婦それぞれの収入を審査してもらい、融資額を最大限にすることができるのがメリットです。
夫婦どちらも住宅ローン減税の恩恵を受けられます。
夫婦とも団体信用生命保険に加入するため、夫婦どちらかに万が一のことがあった場合でも、その分の住宅ローン返済は保険金で完済されることになります。
ただし、どちらかが仕事を辞めた場合、1人で2人分のローン返済をする必要があり、贈与税の課税対象になる可能性もあるというデメリットもありますので、注意が必要です。
ペアローンは住宅ローン2本分なので、1人で借りるよりも多くの額のローンを組む事ができます。
夫婦どちらともローン完済まで働き続ける予定があるか、どちらかに何かあった場合でも一人で返済していける額しか融資を受けないか、どちらかの場合にしか利用しない方が良いです。
| 内容 | どんな人が向いているか | |
|---|---|---|
| ペアローン | 夫婦それぞれの名義でローンを借り、夫と妻、それぞれがローンを返済する。 | 夫婦とも、正社員・公務員など。妻が管理職、専門職等、一生働き続ける強い意志を持っている場合。 |
| 収入合算(連帯債務) | ローン契約者は夫と妻で、夫婦の収入の合計で借り、夫が2人分まとめて返済する。 | 夫婦とも正社員・公務員など。ただし、妻が将来にわたって働き続けるか決めかねている場合には注意が必要。 |
| 収入合算(連帯保障) | ローン契約者は夫で、夫の収入と妻の収入の合計で借り、夫が返済する。 | 片方が正社員でなく、契約社員、派遣、パートなどの場合。 |
妻のパート収入を合算することは可能か?
夫が正社員で、妻がパートという家庭は非常に多いと思いますが、奥さまがパートだったとしても収入合算可能な金融機関はあります。
正社員に比べて審査は厳しくなりがちですが、働き方の多様化に伴い正社員以外にも融資をする銀行が増えてきています。
条件は金融機関によりさまざまなので、借り入れを希望する金融機関で相談をしてみることをおすすめします。
少しでも低金利のローンを探してみる

借りられる額を増やすためには、0.1%までこだわって、金利が低いローンを探すことが重要です。
毎月返済額と返済期間が同じ条件の場合では、一般的に金利が低ければ低いほど利息の負担が軽くなるため、その分だけ借り入れできる額も大きくなります。
また、選ぶ金利タイプでも大きな差が出ます。金利タイプには 『全期間固定金利』、『変動金利』、『固定期間選択型』と大きくわけて3種類がありますが、低金利時代の現在、変動金利が最も安くなっています。
変動金利や固定期間選択型は、返済が終わるまで適用金利や返済額が変動するので、定期的なメンテナンスが必要ですが、将来的な借り換えなども視野に入れ一時的に少しでも安い金利に拘るのも良い選択です。(借り換えの手数料などは掛かります)
頭金をなるべく多く用意する

頭金を多く用意するということは、それだけ金融機関から借入れする金額が少なくて済みます。
借入額が少なくなるということは、冒頭で解説した返済負担率を下げる事になります。
冒頭にも説明しましたが、各金融機関は返済負担率を融資の目安にしていますので、返済負担率を下げることは審査に通る可能性が高くなったり、借入可能額を増やすことができるようになります。
フラット35では、購入する物件価格の10%以上の頭金を用意できれば金利が優遇される、という措置がとられていますので、頭金はなるべく多く用意したほうが良いです。
特にARUHIのスーパーフラットは、自己資金の多さによって金利優遇率が変わります。
自治体の支援制度を活用してみる
お住いの地域や、勤務先の自治体が、融資制度を設けている場合がありますので確認してみましょう。
融資を受けるためにはその地域での一定の居住歴が必要であったり、細かな申し込み資格があり、融資を行っていない自治体や、融資条件は異なります。
住宅金融支援機構のホームページに自治体ごとの融資情報がとりまとめてあります。
具体的な支援の方法には以下3通りのパターンがあります。
- 一般的な金融機関よりも有利な条件で自治体が直接住宅ローン融資してくれるケース
- 金融機関で住宅ローンを借りた後に、一部の利息分を一定期間補填してくれるケース
- 自治体が金融機関に対して、まとまった額の預金を行う代わりに、住宅ローン利用者が有利な条件で融資を受けられるケース
派遣社員、契約社員でも借りられる住宅ローン

長く続く住宅ローンの返済で最も大切なのは『安定かつ継続した収入』がある事です。
契約社員やフリーランスなど、正社員以外で生計を立てる人が増えている今、住宅金融支援機構のフラット35をはじめ、雇用形態を問わない住宅ローンも増えてきています。
しかしながら、条件の良い住宅ローンは審査が厳しいという現実があるため、審査がゆるいローンは制限があったり、金利が高かったりというようなケースが多い傾向があります。
一度に複数の金融機関の事前審査を申し込みすることが可能なサービスを利用して、借入れ可能な金融機関を探してみる手もあります。
正社員でなくても組める住宅ローンの一例
| 金融機関 | 年収 | 雇用形態 | 勤続年数 |
(フラット35) | 特に決まりなし | 特に決まりなし (契約社員・派遣社員、アルバイト・パートでも可) | 特に決まりなし |
(フラット35) | 特に決まりなし | 特に決まりなし (契約社員・派遣社員、アルバイト・パートでも可) | 特に決まりなし |
| 前年度年収200万円以上 | 特に決まりなし (アルバイト・パート、年金収入のみの人を除く) | 特に決まりなし | |
| 安定かつ継続した収入があること | 特に決まりなし | 特に決まりなし | |
| 前年度年収300万円以上 | 正社員・契約社員 (自営業も可) | 2年以上 (自営業の場合は業歴2年以上で300万円以上の所得があること) | |
| 前年度年収100万円以上 | 特に決まりなし (アルバイト、パート年金収入のみの人を除く) | 6カ月以上 | |
| 特に決まりなし | 特に決まりなし | 勤続または営業3年以上 |
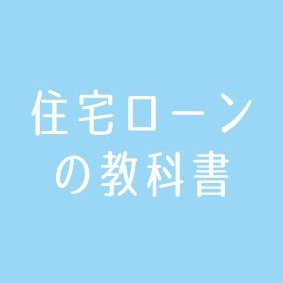
わかりにくい住宅ローン選びの疑問と不安を解消するための情報発信をしています。
Twitterやfacebookでは住宅ローン関連の最新ニュース等を配信。






